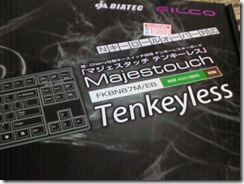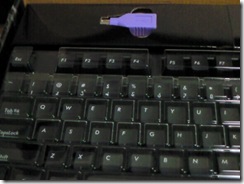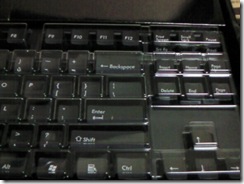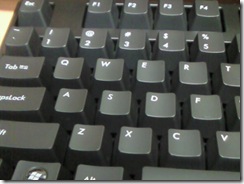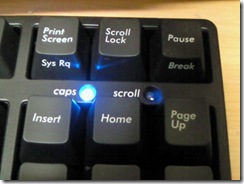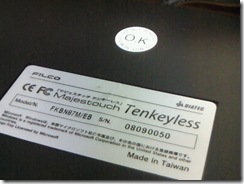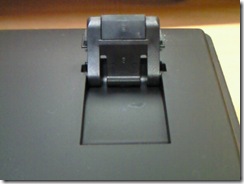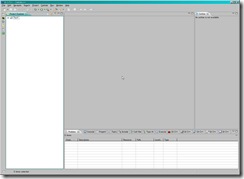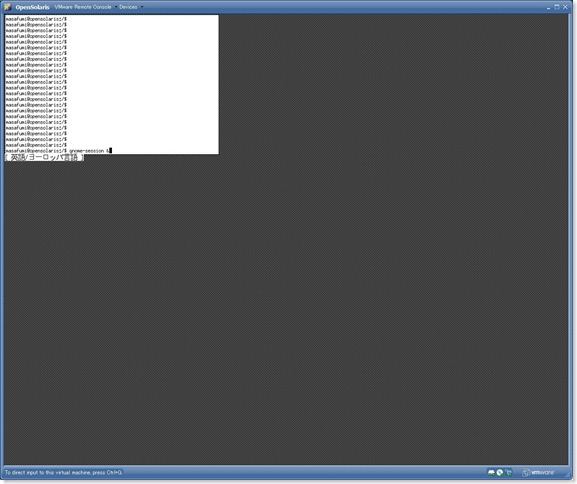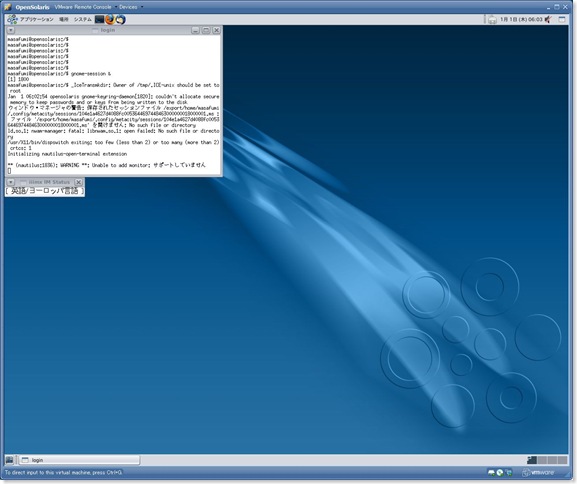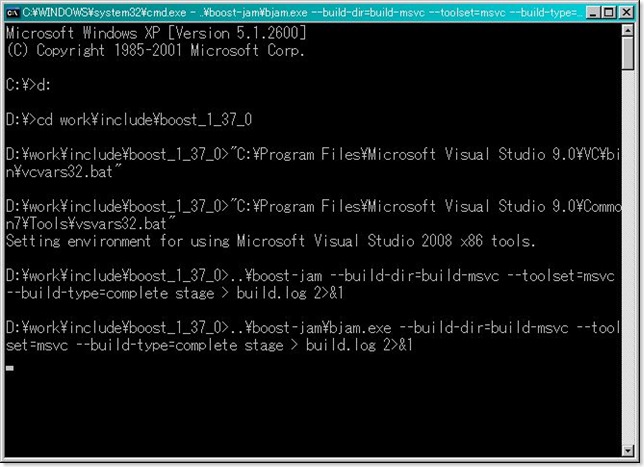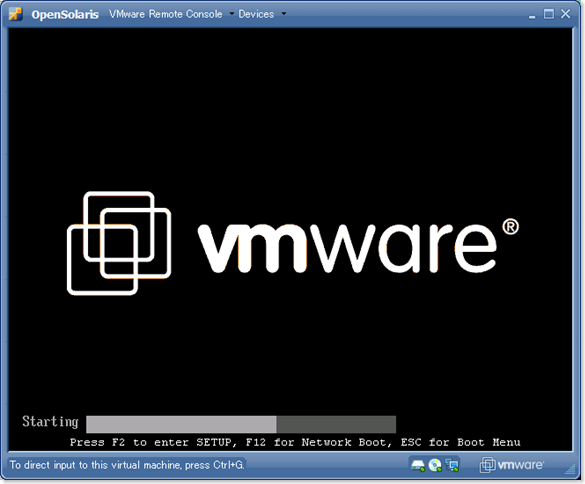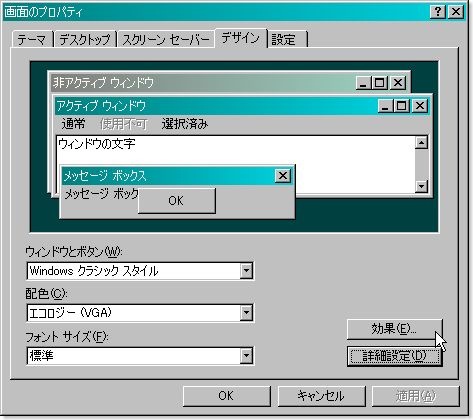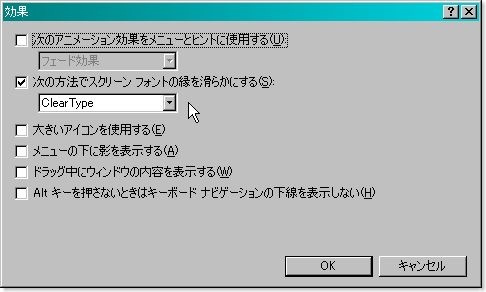この記事は2年以上前に書いたものです。
そのため情報が古い可能性があります。ご了承ください。m(_ _)m
この前のPC入れ替え時になぜか失敗(唐突にリブートしたり)したOpenSolarisを入れてみることにした。OpenSolaris 2008.05のイメージは焼き済みなので、vmware-server側のPCにCDをセットして、http://vmware-serverのインストールサーバ:8222/へアクセス。
早速新しいVirtual Machineを作成する。
Virtual Machine → Create Virtual Machine
Name は、適当にOpenSolariとでもしておく。
OperatingSystem は、Solaris operating system
Version は、OpenSolarisが無かったので、Sun Solaris 10 (64-bit)にした。
Memory は、一杯食うとまずいので、Recommended Minimumの540MBを選択。
Hard Diskは、新たに作るので、Create New Virtual Disk を選択し、Sizeは20GBにしておいた。他の設定はデフォルトのまま。
Network Adapterは、Bridgedを追加。
CD/DVD Driveは、Use a Physical Driveで、物理ドライブ(/dev/hdc)を指定。
Floppy Driveは不要なので、Don’t Add a Floppy Driveを選択。
USBコントローラは一応、Add a USB Controllerを選択。
Finishボタンを押すとVirtual Machineが作成される。
作成されたら再生ボタンを押してVirtual Machineを立ち上げる。
ConsoleタブをクリックするとPluginをインストールするように言われるので、
素直にインストールする。
インストールが完了した後、黒画面をクリックすると↓こんな画面が立ち上がる。
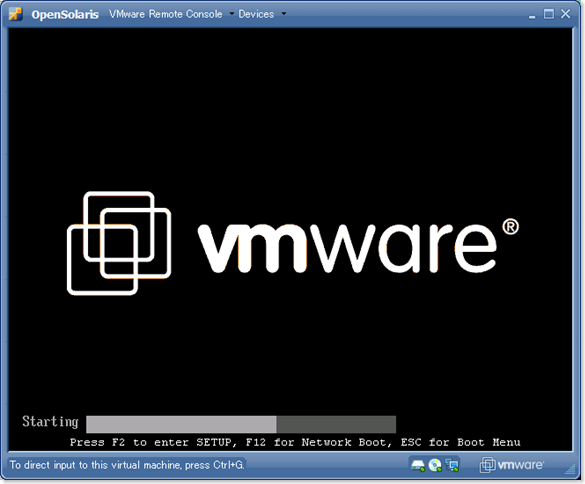
ブラウザ内のJavaアプリで動くのでは無くて安心。(重くならないから)
↑の画面(コンソール)の実態は、
IEの場合
C:\Program Files\Common Files\VMware\VMware Remote Console Plug-in\vmware-vmrc.exe
FireFoxの場合
C:\Documents and Settings\UserName\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\XXXXXXXX.default\extensions\VMwareVMRC@vmware.com\plugins\vmware-vmrc.exe
だそうです。
OpenSolaris 2008.05のCDはセット済みなので、CDの読み込みが始まって、
gnomeが立ち上がる。Live CDなんだって。
デスクトップにあるアイコン「OpenSolarisをインストールする」をダブルクリックすると、OpenSolarisがHDDにインストールされる。
何の問題もなくインストール成功。ScreenShotは撮り忘れた。。orz
prstatとかpstackとか使えますよ!懐かしい!!